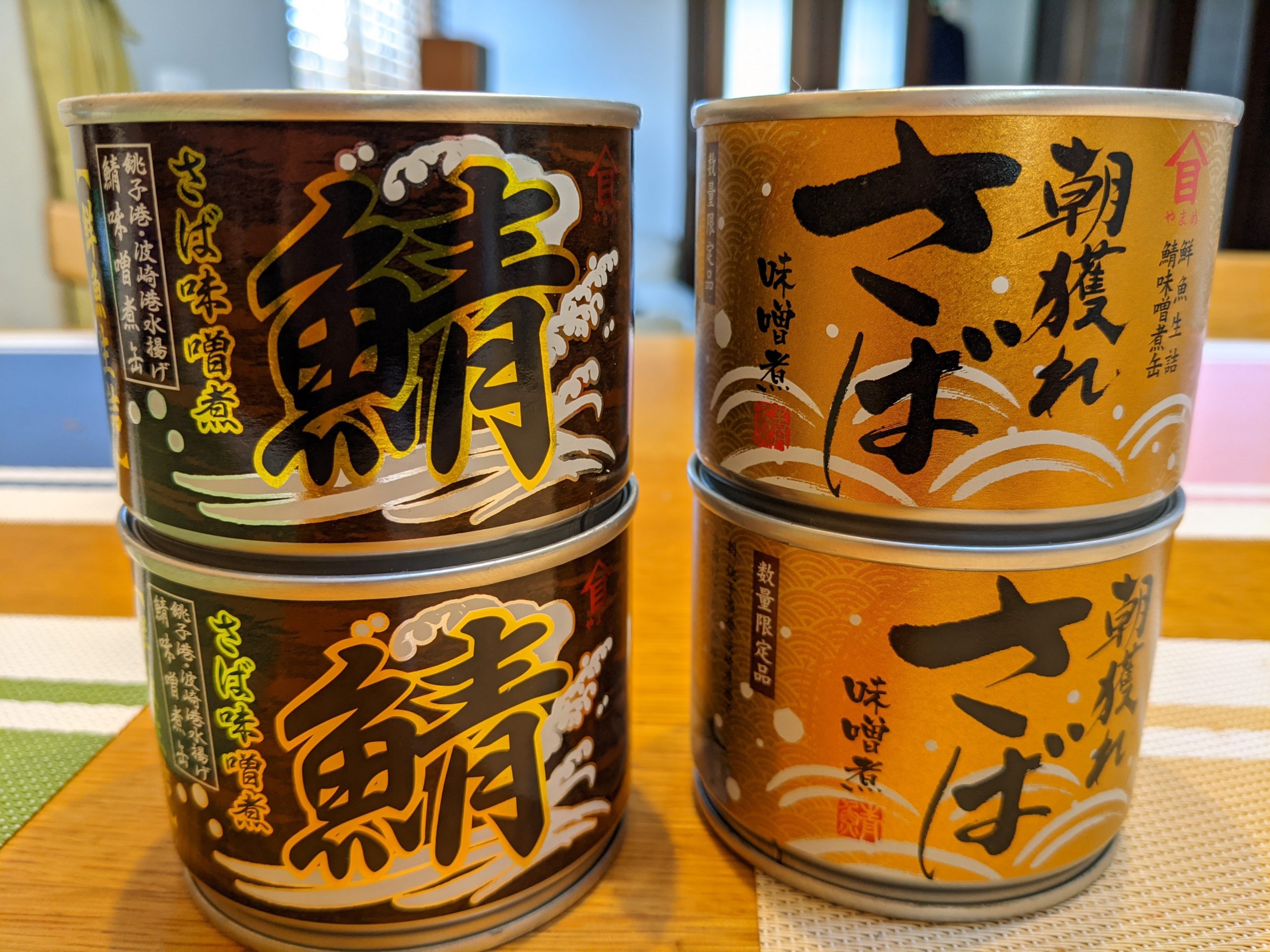娘が看護師国家試験を受けた。本日発表で無事に合格したそうな。よかった。よかった。
ここでは、看護系大学に通わせた親が、だらだらと書いていく。独断と偏見が多いので、話半分で聞いてもらえばいいかと、最初に断っておく。
ここまで来るのにいろいろあった。途中で看護師になるのをやめたいと言い出したのも何回かあった。親としては、そこを何とか踏みとどまって、看護師資格だけは取ってもらおうと何度も説得した。
だって、どんだけ金をかけて大学行かせてたと思っているのかということに尽きる(これが本音)。医療系の大学って、医学部に比べれば安いかもしれないけど、他の学部に比べてものすごく高い。コロナ禍のおかげで大学を行っていないなのに、設備管理料なんて訳のわからないものを取られるし、学生にとっては授業が全部リモートだし、もちろん実習にも行けないし、楽しいキャンパスライフなんてなくなったしで、散々である。親としては、大学の経営収支を見せろや、と言いたい。
最初から、かかったお金の愚痴になってしまった。
今回の看護師国家試験は、本人によると必須の問題はほぼ取れたそうだ。こちらは8割以上取れないと合格できない(法律で決まっているそうな)。その他の問題も8割以上取れたそうだ。これはすごいと思ったら、これでも平均点だそうだ。通っている大学では、ほぼ100%の合格率だそうな。きちんと最低限の勉強をやっていれば合格する試験なのか。娘は一生懸命勉強していたことを見たことないけど、影に隠れて必死に勉強したと信じている。
ところで、この100%の合格率というのは裏がありそうで、大学説明会では謳い文句として合格率が100%と紹介している大学が多い。どうしてそのようなことが起こるかというと、大学は合格しないような学生には最初から受験資格を与えないようである。ではどういうことかというと、不合格になりそうな学生は留年にさせてしまうのである。留年は親にとっては、経済的にとても辛い。再度1年間150万を超える金額の大きな負担となるのである。ここまで来たらやめさせるわけにもいかないから、何とか国家試験の受験資格まで頑張ってもらうことになる。
そこで、もし医療系の大学に志望するのなら、入学説明会でよく言われる国家試験100%の合格率というのを大学を選ぶ際にはあてにしてはいけない。その代わり、どれだけの進級率(反対に留年率と退学率)を調べたほうがいい。大学に聞いても教えてはもらえないとは思うが、留年数はわからないけど入学者数と4年後の合格者数から進学率はほぼわかる。100%の合格率に欺されてはいけない。
就職活動もコロナ禍のおかげで大変な年であった。この年は軒並み募集定員が減らされていた。知り合いの医療関係者によると、病院の経営が大変なことになっているので募集定員を大幅に減らしたそうな。そして、募集期間も短くなっている。娘は、近くの自治体が運営する病院を志望したが、そこがなかなか試験日が決まらず伸ばし伸ばしで、あれよあれよという間に時間が過ぎていた。結局その病院は落ちたけど、まずいことに他の病院は既に募集を終了していた。後は、少ない募集を探しては受けての繰り返しである。ようやく就職先が決まったのは10月である。だから、看護師は就職には困らないというのは、今の状況ではウソである。経験のない大卒の看護師資格を持っているだけでは就職は厳しい。
おそらく、就職しても今までのような新人教育はやってもらえないかもしれない。 病院には急性期と慢性期あるのだそうだが、大卒新人は急性期を目指すものだけと思われていたけど、娘はあえて慢性期の病院に就職した。本人は、亡くなったり急変するような患者を看護したくないそうな。彼女の性格上、のんびりと患者さんと接するほうが合っているので、これは本人にとっても、よい選択かもしれない。
講義もほぼオンラインになってしまったし、看護実習も軒並み中止となっている。娘はコロナ禍の前にほぼ実習が終わっていたので、あまり影響がないと言っていたが、来年度の4年生以下の看護生は満足に実習ができていないのでないか。
そもそも、実習というのは、家族に取っても影響大で、実習期間の前や間では家族もインフルエンザがかかることはもってのほかである。家族がインフルエンザにかかってしまったら、実習自体が中止となってしまうのである。実習が中止になるということは、単位が取れない、すなわち留年確定となる。他の大学では違うかもしれないが、娘が行っている看護大学は、大学医学部と併設ではないので大学付属の病院がない。そこでいくつかの提携している病院に受け入れてもらって実習をしている。実習先の病院では人員の割り当てやスケジュールがあるので、一度実習が中止になると、次は来年となってしまうから留年である。付属の病院がないので実習の振替なんてない。よって、実習期間中というのは、家族にとってもハラハラドキドキなのである。朝も早いし遅刻も厳禁なので、無事に実習を終了するまで、家族総出で相当気を使わなければいけないのである。大学生になったから放って置ければいいのだが、何せ高い授業料を無駄にしないためにも、金を出す親は最後までやり遂げてもらわなければいけないのである。親としては、子どもの将来よりも、こうなったら今までかけてきたお金ほうが大事なのである。看護師資格を取ったら、こっちのものというのが正直な話しである。
前述のように付属病院がある看護大学のほうがいいのか言うと、微妙なところなのである。娘のよう附属病院を持たない大学だと、いろいろな病院に実習に行けて、いろいろな病院を知って、どんな勤務先が自分に合っているかを見極めることができるというのもメリットがある。ただし、そのままエスカレータ式に附属病院に入ることがないので、当然就職活動はキツくなる。反対に、たくさんの就職先の中から選択できるという考え方もできる。
初っぱなの入学式の挨拶で理事長から「大学の先生はプロの教師ではありません。」と言われたそうな。それは小中高と違って、大学で教えるには資格はいらないから、大目にに見てね、ということだったのだろうか。通っている大学の先生というか講師の質も何だか今ひとつのところが見受けられる。途中で休職してしまった卒研担当講師の先生は、就活の最後まで面倒みてくれてよかったが、実習担当の先生の中にはトンでもない指導者もどきも混じっていたそうだ。看護を教えることができる人材がまだまだ少ないのではないかと感じた。大学は、研究、教育、社会貢献といろいろの役割があると思うが、新しい看護大学だと、どれもまだ足りないのではないかと思った。
実習を他の病院に丸投げしてしまうので、実習はたまたたま付いた担当看護師によって天国と地獄に別れるそうである。娘の友だちの中には地獄側にあたったようで、実習担当看護師から看護師の適性がないからと言われたそうで、それが原因で退学してしまった友だちもいた。もっとも適正以前に、大学の講義で看護師になるにあたっての心構えのような講義もなかったようで、何も覚悟もないまま突然野に放り出されたみたいで、とても辛かったのではないかと思った。それと実習も大学から病院に丸投げなので、大学と実習先の病院との連携が足りていない。私から言えば、どうせ実習生なんてお役に立たないので、完璧な看護師なんて求めるのは無理なんで、どうか長い目と温かい目で見てくれないものだろうか。
実習中に実習先の看護師から高圧的な態度を取られたというのも聞いた。しかし、高圧的な態度というのも受け取る側によっては、些細なことでも高圧的であると取れられてしまうので、話半分で聞いたほうがいいかもしれない。だけど、もし実習先の医療関係者が、今まで自分たちの実習経験での趣向返しだったら、早いところこんなことは断ち切ったほうがいい。そんなことして看護師の仲間になろうとしている人たちを減らしてどうするの? 命を預かる大事な仕事だから厳しくして甘くすることができないというはわかるけど、これからも新型コロナウイルスで仕事が大変なことが続くから、優しさと包容力でもっと仲間を増やそうよ。今の人たちは、褒めて伸ばす世代だから。
それと余計な話しだけど、新型コロナウイルスのこの騒ぎで娘が言っていたけど、医療関係者のために感謝のためのライトアップとか垂れ幕とか、全く医療関係者のお腹の足しにならないような話しが多いから、だったら、いただけるお金を増やして、それと待遇改善しろよな、と申していましたとさ。
とにかく看護大学の新設が多すぎである。看護師を増やすというのはわかるけど、今まで医療とは関係なかった文系の大学が、いきなり看護大学を併設するなんて、絶対あんたら金儲けでしょという大学が多い。それと今だに4年制大学にする必要があるのか疑問である。専門性が高い職種は専門学校でいいのではないのか。だったら医学部も昔のように医学専門学校に戻したほうがいいと思うけどな。大学は一般教養が大事だからというのであれば、別に一般教養の大学を作って、そこを卒業してから医療系の専門学校に入って勉強した方が優秀な人材が集まるのではないか。他の分野で一度大学を卒業した人も医療を学び直すということもできるのではないか。しかし、時間もかかるし、お金がかかるし大変だけど、もっと職業訓練の場を広げたほうがいいのではないかと思う。この日本は不必要に大学を作りすぎなのである。
最後のほうは、娘の看護師国家試験合格とは全く関係ないことでした。
追記(2021年4月28日) 現在、自転車で40分かけて病院に通い出しました。雨の日はクルマで送ってあげないといけないので、前日の天気予報はかかせません。送り賃は一回ワンコインです。
さて、娘が入った病院はとんでもなくホワイト(給与、有給以外)らしくて、これは予想外のことで本人は反対に戸惑っている様子です。入る前はすぐ辞めてやると言っていましたが、とりあえず1年行って考えると言っています。
バイトのときも含めて何かといい人にに恵まれるという、娘はそういう星回りに生まれたということでしょうか。
追記(2021年5月5日) そう言えば、娘が勤めている病院で新型コロナウイルスのワクチンを接種してきました。本当に医療従事者になったのだと実感しました。
若さ故に副反応があって、熱は出なかったのですが腕が上がらないそうです。娘からは今後ワクチン接種をするときのアドバイスとしては、被りではなくて前開きのシャツにしてほうがいいそうです。
追記(2021年9月15日) 前の方の追記で、娘が勤めている病院はホワイトと書きましたけど、勤務はホワイトだけど人間関係が闇に近いブラックとのことでした。誹謗中傷などいろいろと問題が抱えているようです。新人看護師の離職率は高そうです。奨学金をもらっていたり寮に入って身動き取れない同期たちは、病みながら働いているそうです。何でそうなってしまうのでしょうか?
おかげで半年で転職すると言い出して、既に退職すると上司にいったようです。
あんたらは看護師ではないから今の仕事はわからない、と言われてしまっていますが、将来はよく考えて進んでもらいたいと思います。
続きはこちらから